| 第120号 |
アカテガニの放仔観察会
 NPO法人小網代野外活動調整会議が毎年夏に開催するカニパトに駅から参加の皆さんをご案内した。
NPO法人小網代野外活動調整会議が毎年夏に開催するカニパトに駅から参加の皆さんをご案内した。
真夏の炎天下、徒歩で干潟まで移動するのはかなりの負担である。参加者の皆さんへバス利用を提案し、ご了承を頂く。ところがこの日は、三浦市のお祭りで幹線道路は大渋滞。油壷行きのバスはいつ着くか分からないという。Mさんのご教示で小網代までバスの利用は諦め急遽、引橋で下車する。この判断は正しかった。
京急バスでは、夏休み期間中のサービスとして、大人1人につき子供1人分が無料となる。今回、家族連れの参加者がおり早速利用できた。
畑の隅にスイカが数多く放置してある。よく見るとアライグマに食い荒らされたような特長のある丸い穴が幾つも開いていた。北尾根の日陰に入ると微かに涼風を感じてほっとする。途中の平坦部でジャコウアゲハとナミアゲハを確認する。
 参加者の皆さん、カニの放仔は始めてだといい期待が高まる様子が感じられる。幾度見ても紙芝居は面白い、説明する人の個性が溢れている。事前研修としては、他の観察会では見られない最高のものである。
参加者の皆さん、カニの放仔は始めてだといい期待が高まる様子が感じられる。幾度見ても紙芝居は面白い、説明する人の個性が溢れている。事前研修としては、他の観察会では見られない最高のものである。
以下「カニパト報告書」から8月14日の様子を要約する。
 日没時、夕焼けの空にくっきりと富士山のシルエットが浮かび上がった。
日没時、夕焼けの空にくっきりと富士山のシルエットが浮かび上がった。
潮位がいつもより高い。日没直後から放仔が始まり、かなりの数が放仔していた。見学者の先頭では、100匹以上の放仔を確認。岩場では数が多く、アカテガニで埋め尽くしていたという。また、アンドンクラゲ、ミズクラゲ、メガロパ、ボラの稚魚採集。日暮れ前に、ハマガニを別荘前で見た等々。
暗い山の端から丸い大きなお月様が昇る。それはじつに童話風の世界で、アカテガニの体内時計の正確さには感心する。来年の夏も恒例として小網代を訪れる家族が増えることを期待したい。
 第22回 小網代の森と干潟を守る会総会
第22回 小網代の森と干潟を守る会総会
平成23年9月4日(日)
13時30分から3時30分
三浦市南下浦市民センター 会議室
はじめに、小網代の森を守る会が1990年に発足し、昨年20周年誌を発行いたしましたが、本来は今年から会の名称が変わり、会としての機能を考えると第1回目の総会となりますが、これまでの経緯もあり、皆様の気持ちを考慮して通算第22回目の総会とさせていただきました。こうした節目に多数の本人出席を得て、加藤議長のもと総会が盛大に開催されました。
今回の総会では、会の名称変更、会則改正、今後の守る会が果たす役割を踏まえた活動方針案、予算案、担当スタッフ案などが原案どおり承認されました。
また、役員スタッフ体制としては、新代表に高橋伸和氏、副代表に矢部、小倉、仲澤の3氏、会計は宮本美織氏にそれぞれ変わりましたが、そのほかはほぼ従来どおりです。
引き続いて、高橋新代表のあいさつでは「17年前に当会がスタートした時の苦労も知らず、ずーと森で活動を続けてきました。ここで代表ということですが、両肩にずっしり責任を感じています。小網代は森と干潟と海がつながっていることに本来の価値があると思っています。また、この森はいつまでも手入れをしていかないと残らないと考えています。これまで開発の問題等消えては残りの波乱の繰り返しでしたが、これからよく自分たちの足元を見て、この森をいつまでも手放さないつもりで頑張っていくつもりです」と、固い決意表明がありました。
そして、休憩後第2部の 岸 由二氏(NPO小網代野外活動調整会議代表・慶応大学教授)の講演会がありましたが、その概要は下記のとおりです。
記念講演 『湿地回復・干潟保全・支援会員・新しい連携』
NPO小網代野外活動調整会議代表理事・慶應義塾大学教授
岸 由二氏
1.湿地回復
小網代の森は昨年2月完全に保全されましたので、すべて、土地が神奈川県のコントール下におかれました。ただ、開発という意味合いから厳密にはこのままではまだ不十分で、さらに次の二つの縛りが必要です。
その一つが、現在、この森は市街化区域で第1種住居専用区域になっているのを市街化調整区域に編入する。二つ目が、首都圏近郊緑地法の特別保護区域にする。
さて、保全は完全に終わったので小網代の森を守る会は、これからの使命を考えて「小網代の森と干潟を守る会」に変更することを私が提案したのです。
かながわトラストみどり財団が小網代の森の保全に本領を発揮するのはこれからだ と期待している。
小網代の森はこれまで40年近く放置され、ここで保全は完了しましたが残っているのは森の管理です。つまり、今後、保全はされたがごちゃごちゃの自然のまま行く可能性だってある。県はいわゆる小網代の森を都市公園的に残す方向はとらず、中央の谷にただ1本の木道と階段を整備するのみのようだ。すべての人はこの森のオープン(H14年春の予定)後はここしか通れない。当守る会も全く例外は許されない。
県として、それでは、山火事や森の湿地の維持などの面で、このまま放っておくわけにはいかず、昨年の小網代対策会議で、「中央の通路が一般公開された後、NPO小網代調整会議が自力で小網代の森の湿地回復をすること」と決定されている。
すでに、当NPO小網代は今年の春から、中央の谷沿線の木の伐採を始めていて、みるみる生物相(カワニナ、アユ、イシマキガイなど)の変化等を確認している。これまで全国規模の助成金を総なめして着実に成果をあげてきたが、さすが保全されるとそうした助成金は今年に入ってすべてアウトとなってしまった。
2.干潟保全
森は公有地になったので、開発はないが干潟については全く保全されていない。
今後、小網代の干潟を残すことは、地元の企業、漁協、リビエラなどにとって有益な事と考えられる。
こうした時、干潟の保全に失敗をするケースとしては、馬鹿な政治運動がおこることです。
NPO小網代は、今後、小網代の数haの干潟やアマモ場をラムサール条約地にする活動を実施していきます。
再三申しているように、これから森の中で保全運動をする必要は一切ない。保全をされた森で泥まみれの土木作業をする。
そこで、これから干潟は、今回名称を変更した趣旨をわきまえ「小網代の森と干潟を守る会」が守ってほしい。この点でNPO調整会議は前面には出ない。NPOは法人なので企業、地元、行政と仲良くやっていかなければならない。守る会なら少しは厳しいことも言えるでしょう。そうした意味で干潟を活用したイベントや観察会をどんどんやってほしい。結果として森も守られることになる。場所も干潟だけではなく、大蔵緑地背後の谷と別荘前ビオトープ湿地周辺を使うことは県の了解がとれている。
3.支援会員
先に言ったとおり、森が保全された、今、企業からの助成金は期待できない。これから当守る会で必要な年間数100万円の資金は『トラスト支援会員』を増やしていくことに尽きると考えている。これまでも各種イベントやカニパトなど機会あるごとに、強くお願いしてきました。今、まったくタダでこうした森の保全活動に参加してくれる学生や市民は皆無でしょう。今現在、小網代に関しての支援会員は300人程度と予想しているが、当面はNPO理事、インストラクターなど身近な方々からの加入促進から始め、これから500人、1000人と増やしていけば、必要な資金はこれだけで確保可能でしょう。こうした自助努力の仕組みがうまく軌道に乗ることは、県やトラストみどり財団にとっても相応しい方向といえる。
さらに、今年6月にはトラスト支援会員のみを対象にした[小網代干潟観察会]も開催され、その中の10人程がフアンクラブに参加という動きにまで来ています。
4.新しい連携
企業等の連携についてはNPO小網代に任せてほしいが、これからは、地元関係者との連携が最大の課題です。
具体的には、地元の漁協、自治会、子供会等との連携による活動です。早速10月15日(土)には三浦市との協力で子供たちを対象にしたイベントが予定されています。
こうした活動をこれから、フラフラせず、逆に戻らないを目標にどんどん前向きに進めていきたい。
記録: 鈴木清市
| 「20年誌」をざっと読ませていただいただけで、守る会の達成感、高揚感、安堵感を感じ、一大イーポックを思いました。スタッフ一同のご健康をお祈りします。
小柳 康蔵
|
3.11大震災!! 自然への畏怖。それ以上に恐ろしいのは人災です。 小さな生命を守り続けておられる守る会の20年誌を読み、活字にならないご苦労を想っています。感謝!! 藤野 秀代
|
| 会の発足、おめでとうございます。皆様の御活躍の日々がよいものでありますように・・・。
佐藤 京子
|
保全が出来、神奈川県の自然の財産です。有難いです。会の皆様に感謝です。
北村 和子
|
 新代表からご挨拶
新代表からご挨拶
第22回総会を終えて
 「小網代の森と干潟を守る会」へ名称変更して最初の総会において承認を受け、仲沢さんから代表を引き継ぎました。
「小網代の森と干潟を守る会」へ名称変更して最初の総会において承認を受け、仲沢さんから代表を引き継ぎました。
森の全面保全が確定した後のあらたな気持ちで、今回の総会を第1回とする案がありましたが、会を解散したわけではなく、また、これまでの歴史のうえに一歩ずつ活動を継続して、未来のこどもたちに「小網代の森と干潟と海」という完結した集水域を残すという目標の道半ばとの自覚から今回の総会を第22回としました。
会員の皆さんはじめ多くの方々の、森を守ろうとの気持ちで団結して活動した永年の成果が実を結び、保全された森の足元である干潟、アカテガニや多くの生き物のふるさとである海に通じる干潟も守らなくてはとの気持ちから、次のステップへ踏み出すことを新しい名称はうたっています。
「小網代の森と干潟と・・・・・地球・・・・・・・・・・ETC. を守る会」までこの使命は未来永劫続くのです。
以上の気持ちで新しい代表は楽しく仕事したいと思っております、皆さんご賛同のうえよろしくご協力お願いいたします。

総会終了後、前代表の仲澤さんへ、
プリザーブドフラワーのリースが「ありがとう」の拍手
とともに贈呈されました。
長年にわたる会長としての活動、お疲れさまでした。
写真撮影:柳瀬
 小網代詩人
小網代詩人
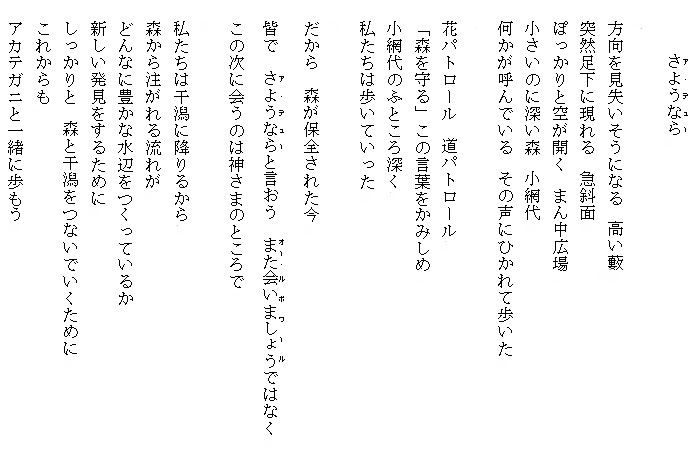
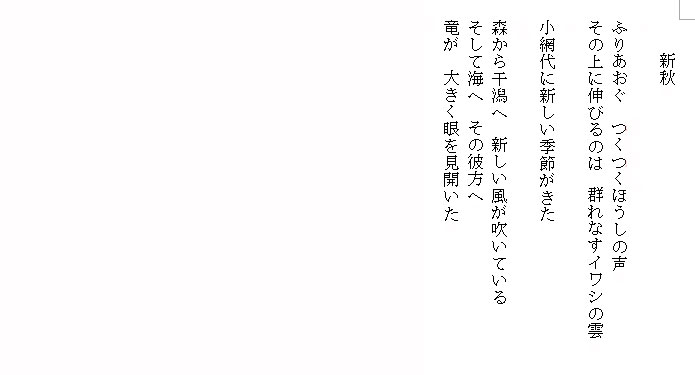
 干潟のゆりかごの小さな住人 その1
干潟のゆりかごの小さな住人 その1
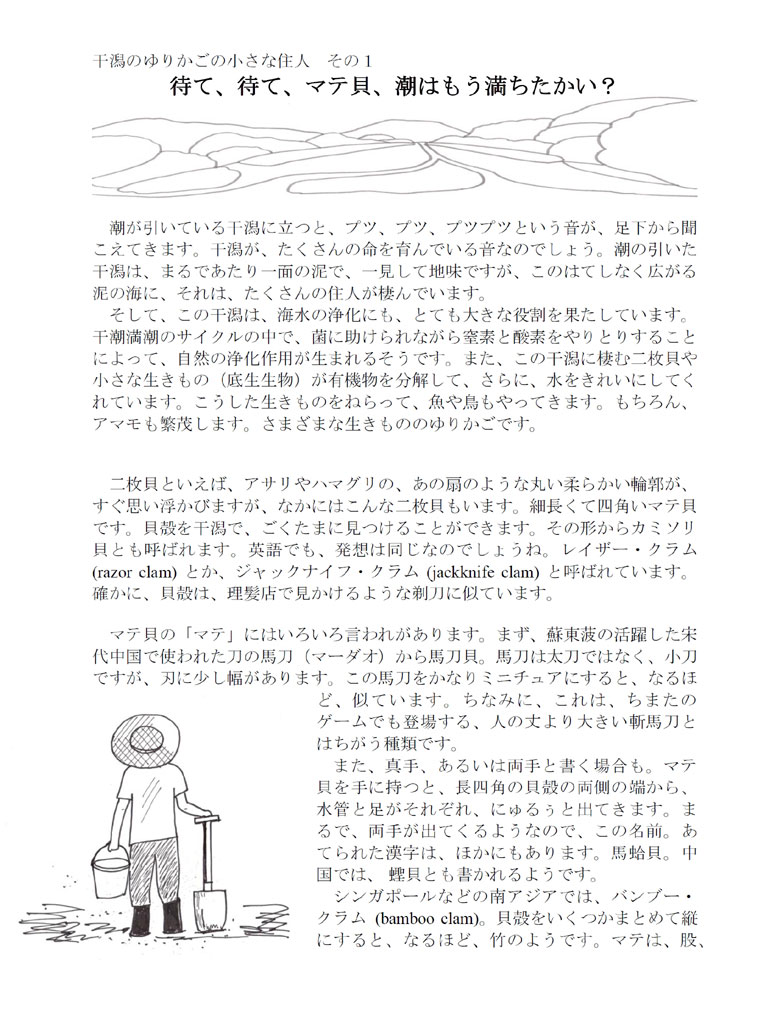
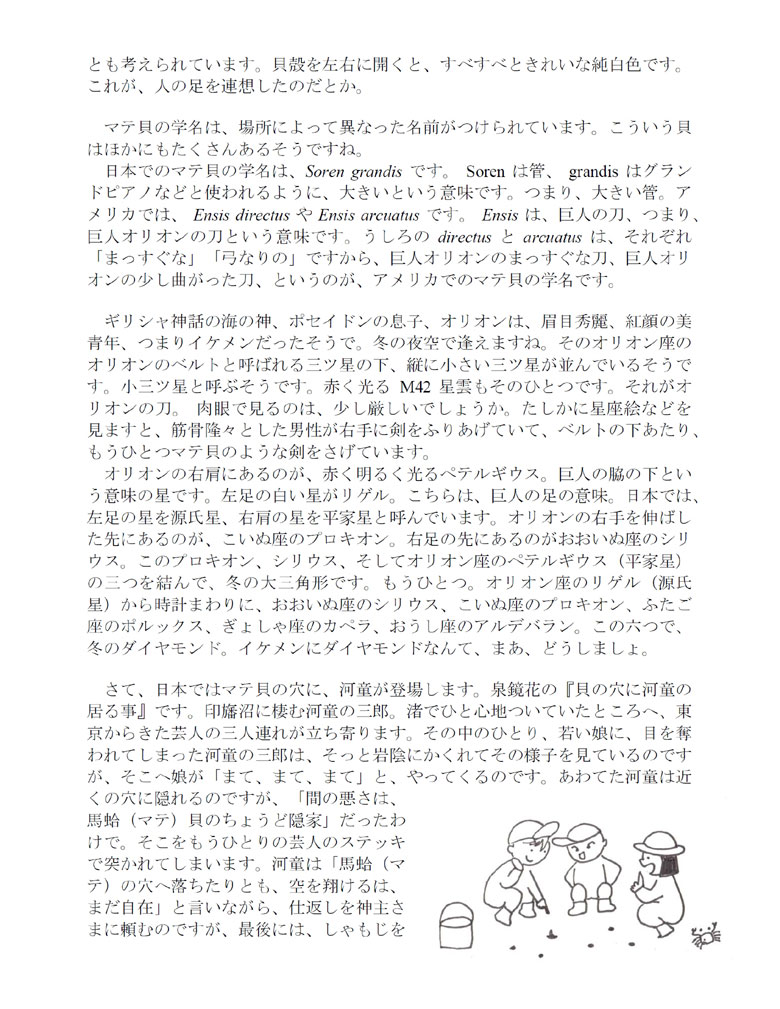

 スタッフコラム
スタッフコラム
長野県辰野町のホタル
諏訪湖を水源とする天竜川、辰野町松尾峡のゲンジボタルは東日本では最大級といわれる。清冽な天竜川が町の中央を流れ、高尾山より高い723メートルの町の位置がホタル発生、生育上での地形的環境に恵まれている。
昔はホタルを捕り放題、他所から商いのために来た人たちも大勢いたという。 高度成長期等、水源の諏訪湖が汚染されて一時激変したが、町や地域の人たちの力強い保護活動が実り戦前のような活気のある生息数へ戻ってきた。
今年のホタル祭は6月17日から26日まで開催。町のHPでは、前日のホタル発生状況を発表している。6月8日初確認、15日1千匹台、17日2千匹台、19日3千匹台、20日4千匹台、21日6,404匹。
それを確認して22日の「あずさ13号」で出発。最終でも帰宅は無理なので、岡谷駅前のホテルへ予約を入れた。この夜は5,558匹、現地は東京ドーム級の広さの生息地で、分水した水路や枝沢が細かく流れている。
19時40分初見、ピークは20時から21時。次第にその数が増えて光の大乱舞である。数百匹のホタルが、一斉に光り消えるといった集団同期明滅現象も確認できた。ホタルが光るというのは、交尾の合図であるという。
この夜は時々雨、遠く雷鳴といった悪条件、それでもこの数であった。21日から27日迄連日5千匹台が続き、7月10日78匹を確認して町の公式発表は終了した。2010年、09年、08年3年連続してピーク時には1万匹以上を確認している。
誰もが必見、感動間違いなしのお勧めホタル観察の一夜であった。
 守る会の活動
守る会の活動
9月4日 スタッフ会議
9月4日 第22回 小網代の森と干潟を守る会総会
 ご寄付ありがとうございます
ご寄付ありがとうございます
小網代の森応援金
| 西川次代
小田島一生 柿田川みどりのトラスト 鈴木清 藤崎洋子 鈴木慶子 盛野重信・雅子 福田みどり 柴内朱美 加藤清子 匿名希望 |
大高義彦
古川太郎 福井すみ代 奥津信子 大川須美 土屋圭子 江川公明 柿島京子 前田信二 井関眞理 |
蓮尾もと子
佐藤美枝子 松林伸子 坪田弥乃子 飯田久仁子 木内恭子 神山喜久栄 高橋宏之 大塚敏 大泉繁子 |
石川登美子
鈴木洋子 金木公子 徳田洋子 塩入一弥 岸 修 嶋津誠 岡見義昭 久水健史 藤崎英輔 |
成相早苗
窪田建平 加藤紀子 小柳康蔵 山岸正平 芥川仁美 神奈川学園 藤間秀代 佐藤高 平野晶子 |
柿本湛子
山室昌代 江尻真 野本哲夫 北村和子 田中幹人 山城謙一 上田尚美 甘露寺信房 吉永浩三 (敬称略)
|
寄付金
| 橋ちひろ | 石川登美子 | 佐藤京子 | (敬称略) |
以上のみなさまにご寄付をいただきました、ありがとうございます。
第107回 自然観察&クリーンのお知らせ
 干潟で楽しむ 紅葉の森
干潟で楽しむ 紅葉の森
晩秋から初冬の小網代の森と干潟には少し遅い紅葉が訪れます。
小網代の森の紅葉を河口の石橋から眺め、宮前の峠を通って白髭神社まで往復、干潟のアシ原の周囲をゆっくりと散策します。森から運ばれたきれいな落ち葉も拾えるかも知れません。アカテガニの冬ごもりも見られるかも。
日 時 12月3日(土) 午前10時 三崎口駅前集合
持ち物 弁当、飲み物、観察用具、雨具、防寒具
案 内 守る会観察会担当スタッフ