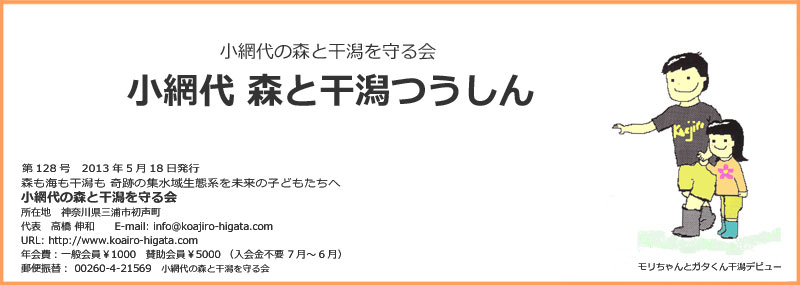
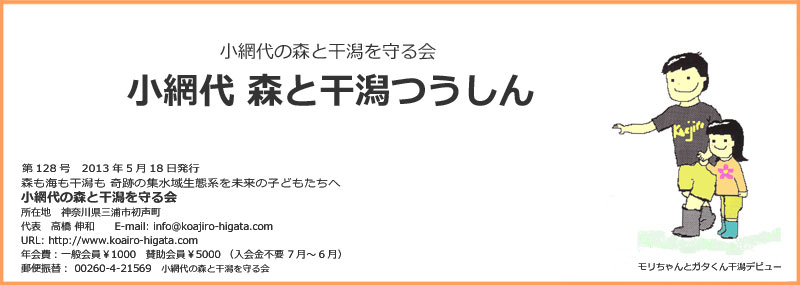 |
| 小網代 森と干潟つうしん バックナンバー |
 普段は目にすることのない、海中の森について想像をめぐらせることができる絶好の機会と待ち望んだ、小網代干潟での海藻の観察会は、穏やかな日差しの中で2月23日に実施されました。
普段は目にすることのない、海中の森について想像をめぐらせることができる絶好の機会と待ち望んだ、小網代干潟での海藻の観察会は、穏やかな日差しの中で2月23日に実施されました。
2013年ゴールデンウイーク前半最終日の4月29日(昭和の日)。三崎口駅には数多くの行楽客が見受けられます。今回の参加者は小学生2名を含む10名(初参加6名)およびスタッフ13名。
定刻に混雑する駅前を出発し、引橋から南側の分水界を歩き干潟にいたるコースを歩きました。
 国道134号を歩きながら相模湾を見渡すと遠方にうっすらと丹沢、箱根、富士山を、後方には大楠山、武山、三浦富士など三浦半島の山々も見ることができました。尾根の上を走る 国道からは三浦半島南部の地形の成り立ちをよく観察することができます。国道わきからすぐに急な崖があり深く複雑な谷をいくつも刻んでいます。一種の溺れ谷のようなもので しょうか。地形図を見ながら歩けば面白さも数倍ましたかもしれません。
国道134号を歩きながら相模湾を見渡すと遠方にうっすらと丹沢、箱根、富士山を、後方には大楠山、武山、三浦富士など三浦半島の山々も見ることができました。尾根の上を走る 国道からは三浦半島南部の地形の成り立ちをよく観察することができます。国道わきからすぐに急な崖があり深く複雑な谷をいくつも刻んでいます。一種の溺れ谷のようなもので しょうか。地形図を見ながら歩けば面白さも数倍ましたかもしれません。
 引橋の交差点で国道はギュッと折れて三浦海岸へ尾根を下っていきます。その尾根が相模湾と東京湾の分水界で引橋を頂点とし、西に流れ、相模湾へそそぎこむ谷が小網代の谷と
いうわけですね。引橋からは小網代の谷を見渡すことができます。新緑に包まれた小網代の谷。さまざまな緑が目に飛び込んできます。一番多いのはコナラの緑。黄色い新葉をふ
きだしたスダジイ。白い花を上に向けて開くミズキ。その中にところどころフジの紫が見られます。新緑の時期はいいですね。
引橋の交差点で国道はギュッと折れて三浦海岸へ尾根を下っていきます。その尾根が相模湾と東京湾の分水界で引橋を頂点とし、西に流れ、相模湾へそそぎこむ谷が小網代の谷と
いうわけですね。引橋からは小網代の谷を見渡すことができます。新緑に包まれた小網代の谷。さまざまな緑が目に飛び込んできます。一番多いのはコナラの緑。黄色い新葉をふ
きだしたスダジイ。白い花を上に向けて開くミズキ。その中にところどころフジの紫が見られます。新緑の時期はいいですね。
 引橋では道路から樹木の上方が目線で楽しめるのも ポイントです。シロダモの出たての新葉に触れるとなんと気持ちのいいことか。カラスザンショウの葉を見て「美味しそう」という参加者。目の前のフジの花からは甘くよい香り
がしました。しばらくは住宅地の中を歩きますが、道端にはフウロソウ科の帰化植物(アメリカフウロ?)やナガミヒナゲシなどが多くみられ、かつて多くみられたオオイヌノフ
グリやヒメオドリコソウなどはほとんどと言っていいほど見られなくなってしまいました。宮前の峠へ下りる手前でジャコウアゲハ、モンキアゲハ、アオスジアゲハなどが飛来
し、目を楽しませてくれました。峠ではいつものようにアカテガニ団地の観察。まだ、動きはあまり見られません。例年ゴールデンウイークには動き始めるので、ここ数日で動き
はじめるでしょう。アカテガニ団地の周りに見られるウラシマソウはすでに花は終わってました。
引橋では道路から樹木の上方が目線で楽しめるのも ポイントです。シロダモの出たての新葉に触れるとなんと気持ちのいいことか。カラスザンショウの葉を見て「美味しそう」という参加者。目の前のフジの花からは甘くよい香り
がしました。しばらくは住宅地の中を歩きますが、道端にはフウロソウ科の帰化植物(アメリカフウロ?)やナガミヒナゲシなどが多くみられ、かつて多くみられたオオイヌノフ
グリやヒメオドリコソウなどはほとんどと言っていいほど見られなくなってしまいました。宮前の峠へ下りる手前でジャコウアゲハ、モンキアゲハ、アオスジアゲハなどが飛来
し、目を楽しませてくれました。峠ではいつものようにアカテガニ団地の観察。まだ、動きはあまり見られません。例年ゴールデンウイークには動き始めるので、ここ数日で動き
はじめるでしょう。アカテガニ団地の周りに見られるウラシマソウはすでに花は終わってました。
 小網代湾の干潟は春の大潮で大きく引いており、チゴガニのダンス、ヤマトオサガニ、コメツキガニ、澪筋にはマメコブシガニが見られました。また、十数羽のチュウシャクシギ?
がお食事の最中でした。 昼食後は浜辺の掃除を行い、ほとんどゴミのないきれいな状態となり、初夏のような汗ばむ陽気でしたが、参加者からは笑顔がこぼれていました。帰り道は新しく開設された北尾根
の階段を息をハアハアと切らせながら一気に上りつめ帰途につきました。
小網代湾の干潟は春の大潮で大きく引いており、チゴガニのダンス、ヤマトオサガニ、コメツキガニ、澪筋にはマメコブシガニが見られました。また、十数羽のチュウシャクシギ?
がお食事の最中でした。 昼食後は浜辺の掃除を行い、ほとんどゴミのないきれいな状態となり、初夏のような汗ばむ陽気でしたが、参加者からは笑顔がこぼれていました。帰り道は新しく開設された北尾根
の階段を息をハアハアと切らせながら一気に上りつめ帰途につきました。
どの花も例年より1週間以上早いようですが、昆虫その他の動物は例年と変わらないような気がします。この春の寒暖の差の大きさが問題と考えられますが、地球温暖化も一因でしょうか。
※ 観察会はNPO法人小網代野外活動調整会議と共催で実施し、アカテガニ広場や倉庫を使わせていただきました。
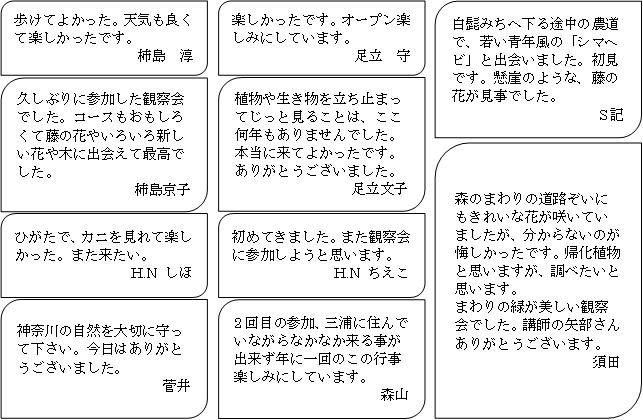
小網代の干潟の周辺で暮らすヤドカリの仲間は7種くらいです。
ヤドカリの仲間の中で小さなハサミを持ち、ハサミを水平に開閉するのがヤドカリ科のヒメヨコバサミ属とヨコバサミ属です。小網代の干潟にはヒメヨコバサミ属のヤドカリが2種類
(ケブカヒメヨコバサミPaguristes ortmanni Miyake 1978、ブチヒメヨコバサミPaguristes japonicus
Miyake,1961)とヨコバサミ属のヤドカリが2種類 (イソヨコバサミ(Clibanarius virescens(Krauss,1843))、コブヨコバサミ)暮らしています。 小網代の干潟に暮らすヤドカリの中で一番大きいのがコブヨコバサミ ( Clibanarius infraspinatus Hilgendorf,1869)です。コブヨコバサミという名前はハサミ脚の長節の基部にこぶ状の突起が一つあることから名づけられたようです。
コブヨコバサミはインド洋、オーストラリア、東南アジアから日本までとても広い地域に分布しています。
小網代の干潟に暮らすヤドカリの中で一番大きいのがコブヨコバサミ ( Clibanarius infraspinatus Hilgendorf,1869)です。コブヨコバサミという名前はハサミ脚の長節の基部にこぶ状の突起が一つあることから名づけられたようです。
コブヨコバサミはインド洋、オーストラリア、東南アジアから日本までとても広い地域に分布しています。 コブヨコバサミの仲間、Clibanarius属は、熱帯域と暖かい温帯域を中心 に世界的に59種くらいがサンゴ礁海岸や岩礁海岸あるいは河口の干潟などに暮らしています。日本とその近海で見られるコブヨコバサミの仲間は暖かい海域のサンゴ礁や干潟の
潮間帯、亜潮間帯を中心に多く見られ、甲殻類図鑑を見ると12種類が載っています。しかし分類はかなり混乱しているようでまだ名前が変わるかもしれません。ヨコバサミの仲間
のヤドカリのハサミは左右ほぼ同じ大きさですがオスでは右のハサミが大きい種が大半で、特に大型の個体では顕著のようです。また、この仲間は「長指型」と「短指型」の種があ
るようで、「長指型」は歩脚が細長く大型の種が多く含まれ、「短指型」は歩脚の指節が前節より短く小型の種が多いようです。
コブヨコバサミの仲間、Clibanarius属は、熱帯域と暖かい温帯域を中心 に世界的に59種くらいがサンゴ礁海岸や岩礁海岸あるいは河口の干潟などに暮らしています。日本とその近海で見られるコブヨコバサミの仲間は暖かい海域のサンゴ礁や干潟の
潮間帯、亜潮間帯を中心に多く見られ、甲殻類図鑑を見ると12種類が載っています。しかし分類はかなり混乱しているようでまだ名前が変わるかもしれません。ヨコバサミの仲間
のヤドカリのハサミは左右ほぼ同じ大きさですがオスでは右のハサミが大きい種が大半で、特に大型の個体では顕著のようです。また、この仲間は「長指型」と「短指型」の種があ
るようで、「長指型」は歩脚が細長く大型の種が多く含まれ、「短指型」は歩脚の指節が前節より短く小型の種が多いようです。
 日本ではコブヨコバサミと呼ばれていますが、外国では歩脚にオレンジ色の縦のラインがあるのでストライプトハーミットクラブと呼ばれるようです。小網代のコブヨコバサミが利用する貝殻はアカニシ、ナガニシ、ツメタガイ、サザエ、ヤツシロガイですが、小さな個体はホソウミニナやイボニシ、ヒメヨウラクなども利用しています。日本のコブヨコバサミと同じ仲間のアメリカのコブヨコバサミ(Clibanarius
vittatus Bosc,(1802))はアメリカ大陸の大西洋沿岸のバージニアからブラジルまで非常に広い範囲にわたって干潟を中心に暮らしており、アメリカでは脚に白いスジ
があるのでアメリカのコブヨコバサミもストライプトハーミットクラブと呼ばれているようです。
日本ではコブヨコバサミと呼ばれていますが、外国では歩脚にオレンジ色の縦のラインがあるのでストライプトハーミットクラブと呼ばれるようです。小網代のコブヨコバサミが利用する貝殻はアカニシ、ナガニシ、ツメタガイ、サザエ、ヤツシロガイですが、小さな個体はホソウミニナやイボニシ、ヒメヨウラクなども利用しています。日本のコブヨコバサミと同じ仲間のアメリカのコブヨコバサミ(Clibanarius
vittatus Bosc,(1802))はアメリカ大陸の大西洋沿岸のバージニアからブラジルまで非常に広い範囲にわたって干潟を中心に暮らしており、アメリカでは脚に白いスジ
があるのでアメリカのコブヨコバサミもストライプトハーミットクラブと呼ばれているようです。
ヤドカリが利用する貝殻の好みについてコブヨコバサミ( Clibanarius infraspinatus)を観察して調べた研究があります。ヤドカリは通常体に丁度合った貝殻を利用します。
しかし丁度よい貝殻が見つからないときには少し小さめだったり、大きめの貝殻を利用しています。そこで、
その1:コブヨコバサミを野外で集められた貝殻のある状態、
その2:小さすぎる貝殻での状態、
その3:大きすぎる貝殻での状態、
その4:過剰の貝殻のある状態、
の4つの状態で飼育しました。
このあとヤドカリに自由に好みの貝殻を選択させると、小さすぎる貝殻に制限されたヤドカリは他の状態のヤドカリよりも小さな貝殻を選択しました。しかし、大きすぎる貝殻を 利用するヤドカリや自由に貝殻を選べるヤドカリは貝殻の選択に変わりがありませんでした。このようなことからヤドカリの貝殻の好みは最近の経験や過去の経験までに依存して いるようです。ヤドカリも小さな家に暮らしていると大きな家では何となく落ち着かなくなるのでしょうか。
アメリカのコブヨコバサミ(Clibanarius vittatus)では季節移動などさまざまなことが調べられています。
フォスリンガム先生の研究によるとテキサス州(ガルベストン湾?)のアメリカコブヨコバサミは大きなオスが夏から海岸を離れ深い場所に移動をはじめ小さなメスは晩秋に移動し
て春に再び海岸に戻るようです。
 サンドフォード先生の研究によるとフロリダのドックアイランドではアメリカのコブヨコバサミは夏には海岸のヤドカリの優先種であるが冬期にはほとんど見られないとあります。
そして夏季には多くの個体が陸上で見られ、何日間も陸上にいることができるようです。
サンドフォード先生の研究によるとフロリダのドックアイランドではアメリカのコブヨコバサミは夏には海岸のヤドカリの優先種であるが冬期にはほとんど見られないとあります。
そして夏季には多くの個体が陸上で見られ、何日間も陸上にいることができるようです。
ローリー先生とネルソン先生の研究によるとフロリダでは晩秋に深い場所に移住し4月に海岸に戻ってくるとあります。しかし、メスと小さなオスはそのまま海岸に残っているよう
です。そしてフロリダのアメリカコブヨコバサミ(Clibanarius vittatus)は海藻のエリアでは端脚類、タナイス類、ヒモ形動物などを食べ、砂地のエリアでは多毛類、等脚類を
食べています。また干潟のスカベンジャーとしてバイオターべーション(生物撹乱)を起こし、他の底生動物相に影響を与えているとあります。
小網代の干潟のコブヨコバサミは春から夏に干潟の上の方でも大きな個体がたくさん見られます。しかし、寒い冬には潮が大きく引いたときでも干潟の下の方の水中でわずかに
出会えるだけです。このようなことから小網代のコブヨコバサミもアメリカのコブヨコバサミと同じように寒い冬季には深い場所に移住して暖かい春が来るのを待つようです。
ストライプトハーミットクラブ(Clibanarius vittatus)と同じように縞模様のあるヤドカリとかオレンジ色の脚のヤドカリとして知られているヤドカリがハロウィーン ヤドカリ
( Ciliopagurus strigatus (Herbst,1804) ;日本名ベニワモンヤドカリ )です。このヤドカリはアクアリウムを楽しむ人に人気があります。ハロウィーンヤドカリは沖縄や
ハワイ、インドネシアなどサンゴ礁のリーフの周りで見られます。小網代干潟のコブヨコバサミもカボチャの産地三浦にちなんで小網代ハロウィーンヤドカリとしては・・・。
参考資料:朝倉彰先生の研究(2005), 原色日本大型甲殻類図鑑(1)三宅貞祥 著、保育社、
1982, ブライアン ハーツレット先生の研究(1996), ニック フォスリンガム先生の研究(1975),
フロイド サンドフォード先生の研究(2003),
ウエンディー エー ローリー先生とワルター ネルソン先生の研究(1988)
大澤先生の研究(2009)
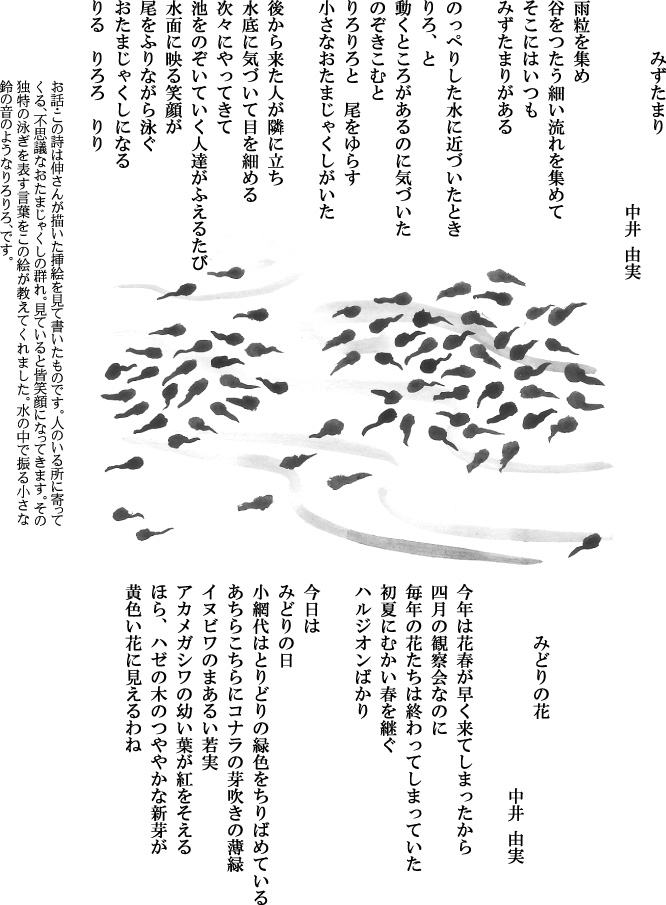
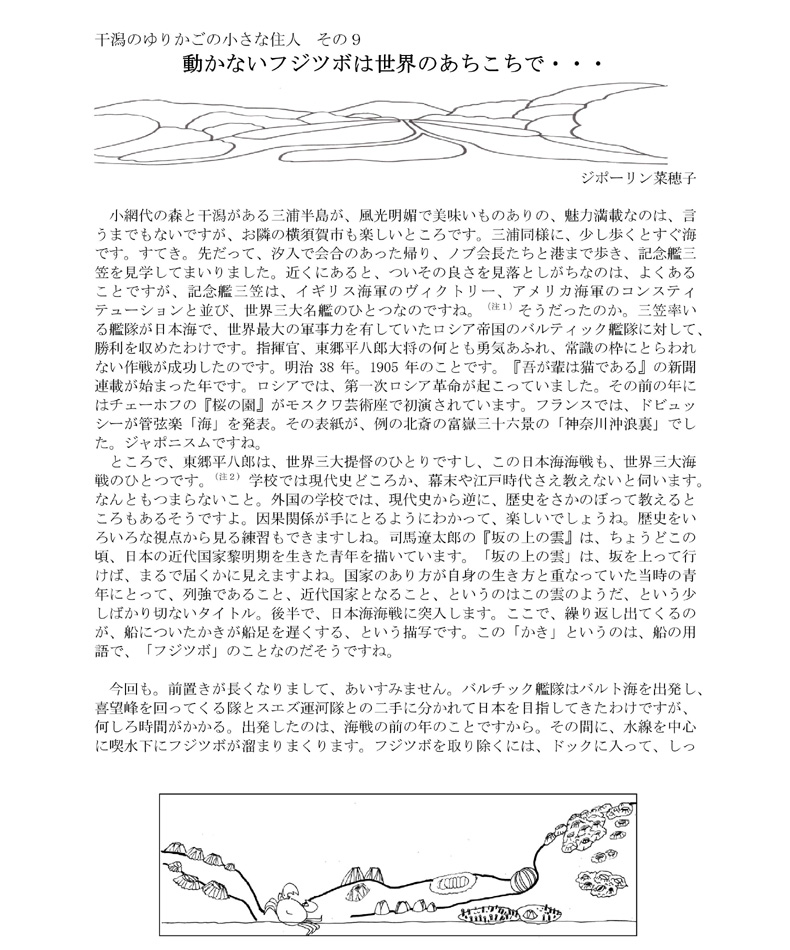
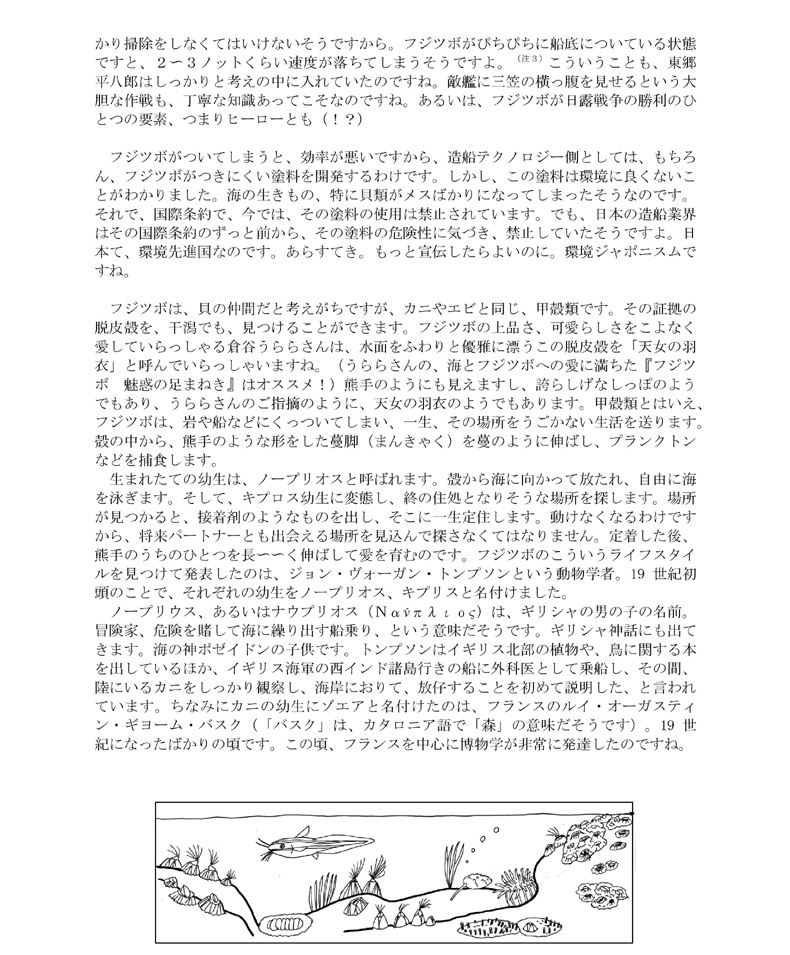
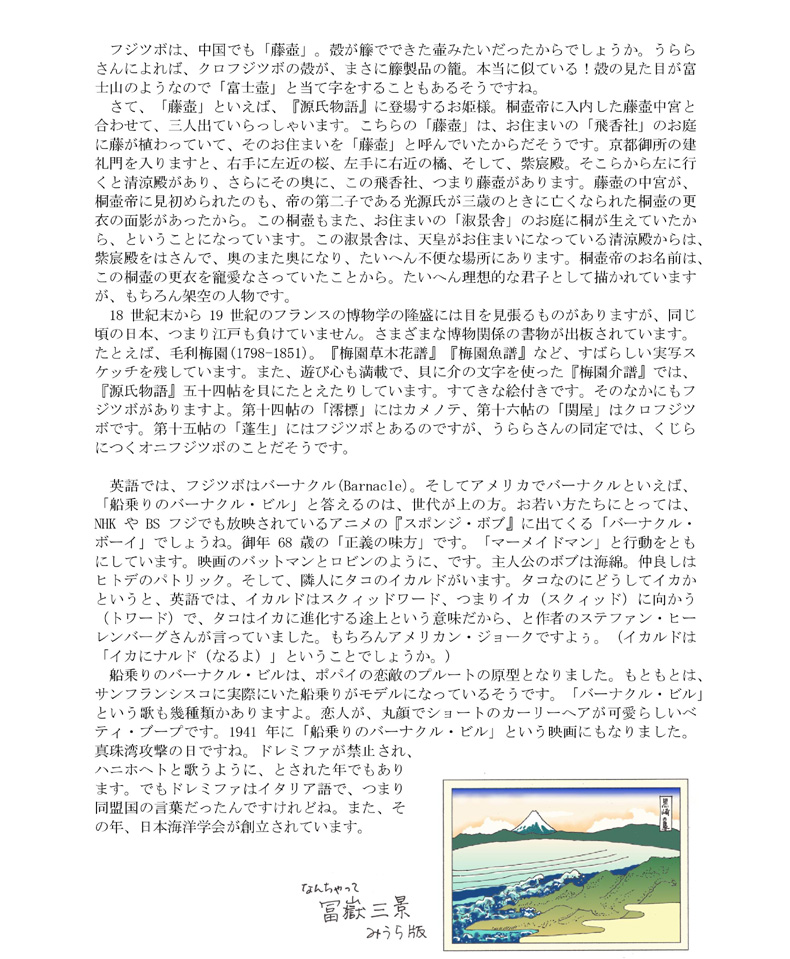
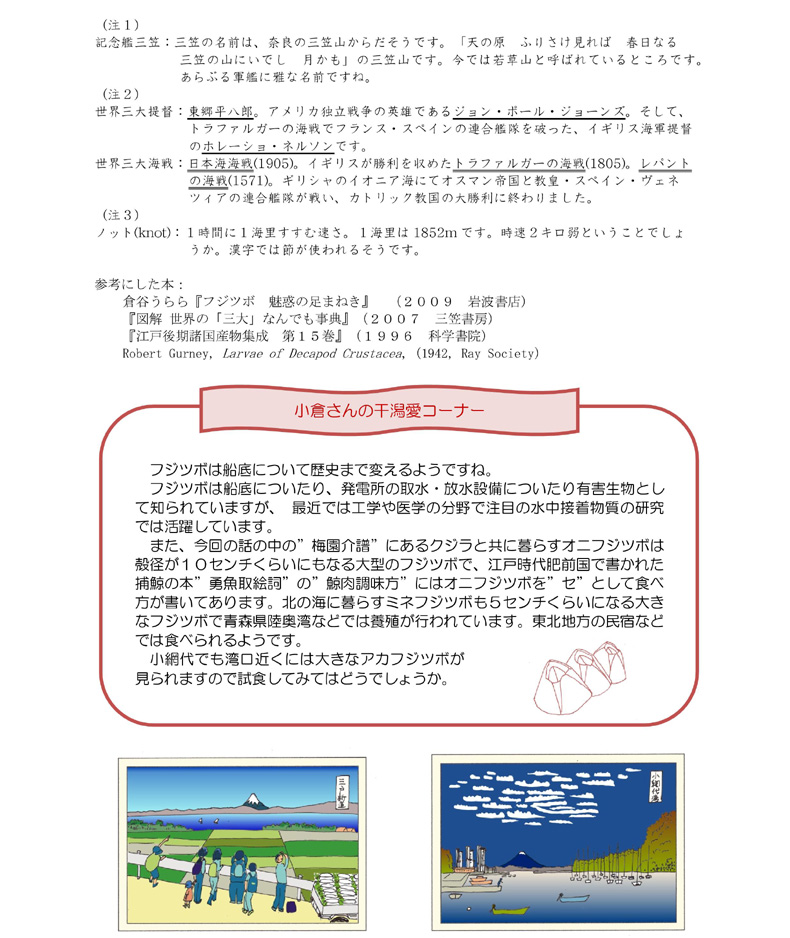


 |
 |
 |
| No.6 知り合いの知り合いの伝手で、作って もらった赤いフエルトのマスコット 目玉が目玉 |
No.7 県サポのともしびショップ で見て、作業所に頼んで作って もらった。ビーズにフェルトの足、 色がいろいろ。何度も制作を お願いした。 |
No.8 三浦のきくな作業所に作って貰った袋。 アカテガニのステンシルが可愛い。 結構評判がよかった。 今も使っているスタッフがいる。 |
 |
 |
 |
| No.9 同じくきくな作業所に作って貰った。 テラコッタ粘土にカニが可愛く描いてある。 うらに磁石が貼り付けてある。 |
No.10 今は陶芸工房Gを主宰されて いるK先生の若い頃に、型を 作って貰い、三崎の作業所で 指導して焼いてもらった。 かにのマグネット |
No.11 Kさんが初めて小学校の子供を小網代 の森につれてきた後で、子供が描いた絵を シールにして貰った。ちなみにお母さんは その時、カワセミの絵を描いてシールにして くれた。 |
*1 現在「アカテガニ募金」はNPO法人小網代野外活動調整会議が預かり、トラスト財団に寄付をしています。
*2 現在カニパトロールはNPO法人小網代野外活動調整会議が実施しています。
| 2/23 | スタッフ会議(引橋 総合福祉センター) |
| 2/24 | 公益社団法人日本ナショナルトラスト協会全国大会参加 |
| 3/23 | 通信127号印刷(横須賀市市民活動サポートセンター) |
| 3/23 | はまかぜ新聞に4/29自然観察&クリーンの広告をリリース |
| 4/29 | 第114回自然観察&クリーン「小網代の春を感じよう」 |
| 4/29 | スタッフ会議(引橋 総合福祉センター) |
| 会の活動費 | 矢部和弘様 |
| 森の応援金 | 福井すみ代様 野内真理子様 大川須美様 小倉雅實様 仲澤イネ子様 杉崎泰章様 竹内晶子様 高橋伸和様 浪本晴美様 別府史朗様 松原あかね様 山本述子様 宮本美織様 橋 美千代様 鈴木清市様 鈴木カヲル様 |
| 以上の方からご寄付をいただきました、ありがとうございました | |
 トップページの左側のボタンは上から |
トップページの上部です。ページの右側には小網代の森に関する注意やお知らせ、NPO法人小網代野外活動調整会議の紹介とリンクがあります。 下の方には最新の出版物の紹介や、更新情報、潮位表などがあります。 | |||||
http://www.koajiro-higata.comgoogleやyahooで、「こあじろひがた」を検索するとすぐに見つかります |
||||||
| ・小網代の森と干潟ってどんなところ ・守る会について ・森と干潟つうしん ・小網代の出版物 ・リンク ・お問い合わせ ・会員専用ページ Etc.へのリンクになっています。 |
画面左側のボタン | |||||
| |
森と干潟つうしんのボタンをクリックすると | |
 |
つうしんを読んだり、会員専用ページを開いたりなどなど、ホームページの主なコンテンツを見ることができます。 | ||
| 守る会についてのボタンをクリックすると | |
 |
会の目的や沿革など守る会の情報が・・・ | |||
| 今年は小網代のサクラもフジの花も少し早く満開となりました。もう干潟ではマメコブシガニが食事やお嫁さん探しに忙しく動き回っているのが見られます。 干潟のカニたちも忙しい季節を迎えています。元気いっぱいの干潟の生き物を見てリフレッシュしてはいかがでしょう。 | ||||
| 日 時 | : | 2013年6月15日(土) | ||
| 集 合 | : | 10:00 京浜急行三崎口駅改札前(トイレがありませんので必ず駅で済ませてください) | ||
| 解 散 | : | 14:00ころ 現地解散 |  |
|
| 講 師 | : | 小倉雅實氏 | ||
| 参加費 | : | 無料 | ||
| 申し込み | : | 当日現地で受け付けします | ||
| 持ち物 | : | 長靴、お弁当、飲み物、雨具 小さなお子さまは着替えもあると安心です。 そのほか図鑑や虫眼鏡、双眼鏡などの観察用具もあるとより一層楽しめます。 |
||
| お問合せ | : | 046-889-0067(仲澤) | ||
|
小網代 森と干潟つうしん NO.128 2013年5月18日発行 森も海も干潟も 奇跡の集水域生態系を未来の子どもたちへ |