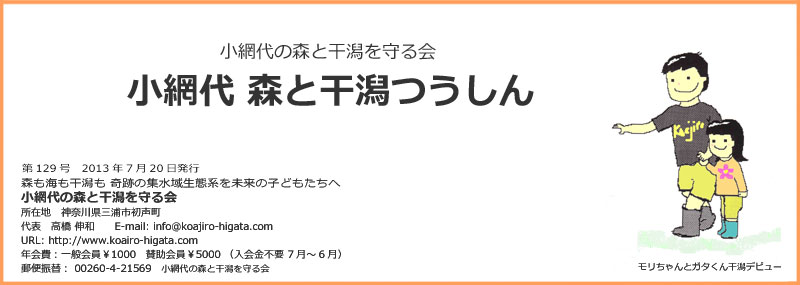
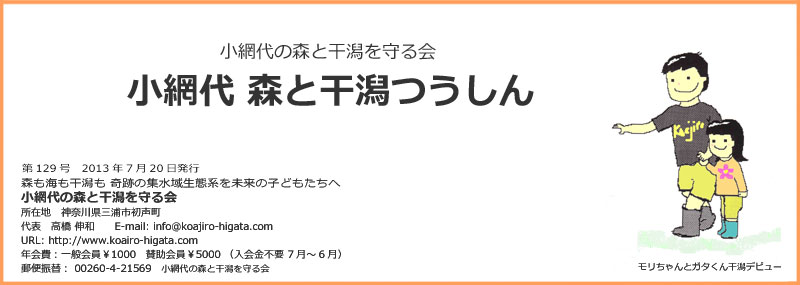 |
| 小網代 森と干潟つうしん バックナンバー |
 今回の観察会は干潟のカニや貝の観察が目的です。大蔵緑地で長靴に履き替え採集用のバケツと網をもらって干潟へ向かいます。潮の引き具合があまり良くないとの予想でしたが、河口の石橋から干潟に入ると少しずつ潮が引いてきてチコガニたちが元気に出迎えてくれました。毎度見慣れたはさみ振りの光景ですが何度見てもつい見つめてしまうひょうきんな動作に、初参加者の皆さんはそれこそ歓迎を受けているように感じるひとこまです。はさみを上げたときに見える青紫色のおなかの模様がひときわくっきり美しく輝きます。子供たちは捕まえようと手をのばしますが、そのたびにサット穴の中へ逃げ込まれ延々とモグラたたきならぬカニたたきを続けています。
今回の観察会は干潟のカニや貝の観察が目的です。大蔵緑地で長靴に履き替え採集用のバケツと網をもらって干潟へ向かいます。潮の引き具合があまり良くないとの予想でしたが、河口の石橋から干潟に入ると少しずつ潮が引いてきてチコガニたちが元気に出迎えてくれました。毎度見慣れたはさみ振りの光景ですが何度見てもつい見つめてしまうひょうきんな動作に、初参加者の皆さんはそれこそ歓迎を受けているように感じるひとこまです。はさみを上げたときに見える青紫色のおなかの模様がひときわくっきり美しく輝きます。子供たちは捕まえようと手をのばしますが、そのたびにサット穴の中へ逃げ込まれ延々とモグラたたきならぬカニたたきを続けています。
 そこでジャジャーンと現れた助っ人が、今回の観察会の初めに参加者の皆さんにおもとめいただいたNPO小網代野外活動調整会議が発行した「小網代干潟観察安全ガイド」です。ほんの一枚の絵地図ですがこの
ガイドを片手にぐるっと周囲を見渡すとあらあらふしぎ、さっきまで見えなかったさまざまな干潟の生き物が自分の足元にざわざわとうごめいているのが見えてきます。ほんとうに足の置き場にこまってしまいます。干潟を歩くときは澪す
じを通りましょうという意味がよくわかります。今回ゴムぞうりを持参した方がおられましたが、干潟には危険な生き物や、危ない貝殻などもあり、ぜひ長靴をご用意ください。
そこでジャジャーンと現れた助っ人が、今回の観察会の初めに参加者の皆さんにおもとめいただいたNPO小網代野外活動調整会議が発行した「小網代干潟観察安全ガイド」です。ほんの一枚の絵地図ですがこの
ガイドを片手にぐるっと周囲を見渡すとあらあらふしぎ、さっきまで見えなかったさまざまな干潟の生き物が自分の足元にざわざわとうごめいているのが見えてきます。ほんとうに足の置き場にこまってしまいます。干潟を歩くときは澪す
じを通りましょうという意味がよくわかります。今回ゴムぞうりを持参した方がおられましたが、干潟には危険な生き物や、危ない貝殻などもあり、ぜひ長靴をご用意ください。
※ 観察会はNPO法人小網代野外活動調整会議と共催で実施し、アカテガニ広場や倉庫を使わせていただきました。
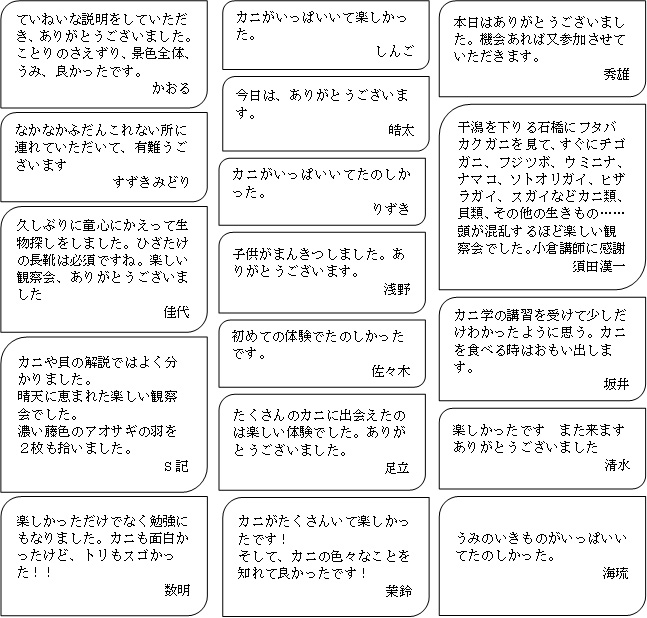
 貝の仲間、軟体動物は巻き貝、二枚貝など大きく分けると8つのグループがあります。
貝の仲間、軟体動物は巻き貝、二枚貝など大きく分けると8つのグループがあります。*軟体動物の一般的な発生様式は卵割後にトロコフォア幼生からベリンジャー幼生を経て成体になります。巻貝類、二枚貝類はこのように発生しますが、ヒザラガイ類ではトロコフォア幼生から変態 して成体になります。
参考資料: 海の味―異色の食習慣探訪―、山下欣二著、八坂書房、1998 日本貝類方言集、川名輿、未來社、1998年 千葉生物誌24(1,2) 千葉県生物学会、1975 三浦半島の民俗Ⅰ 神奈川県民俗調査報告④、神奈川県立博物館、1971 遺伝、vol.41,no.4;1987 遺伝、vol.55,no.3;2001 アメリカの大学のダニエル、スパイザーさんの研究
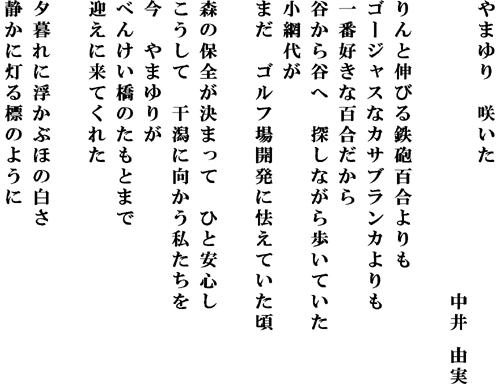

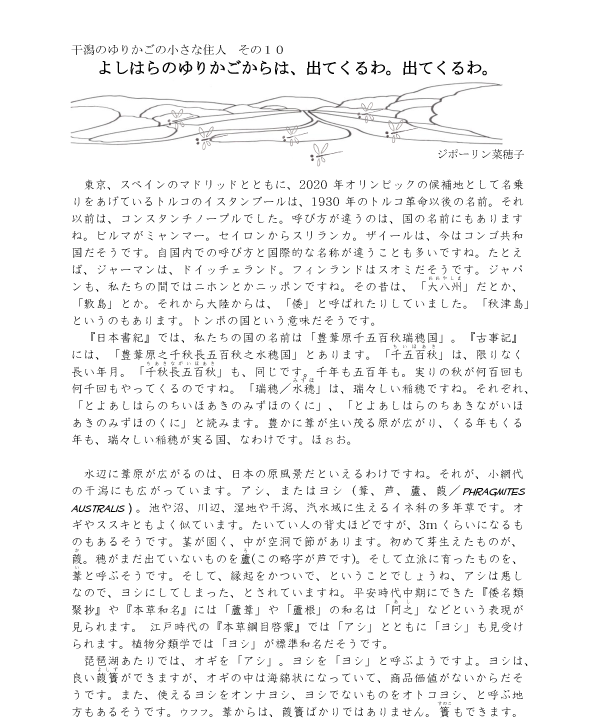
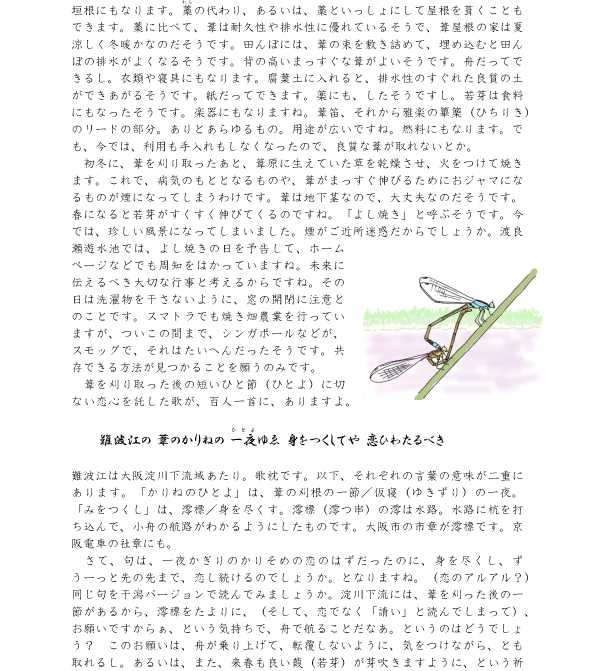
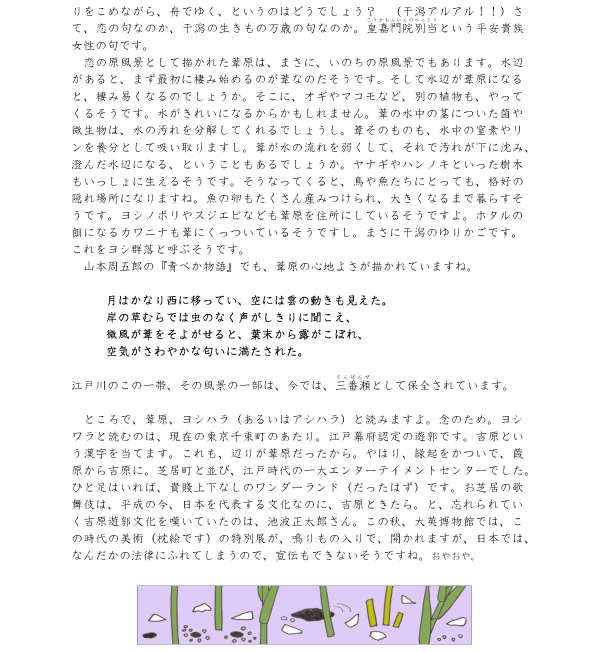

 |
No.12 リユース防水でかバッグ 廃棄されたカニパトのユニフォームの胴長靴の使える部分で作った防水バック、カニ柄の布にカニパトで使っていたフエルトのカニバッジを縫い付けました。世界で唯一の作品です。細かい所には目をつぶって下 さい。 |
|
 |
 |
|
| No.13 カニをデザインした小さな陶器のいれもの 高さ10cm程度、ドライフラワーなら確実に、 水漏れがなかったものに当たった方は超ラッキー。三浦で育ったオオシマザクラを焼いてできた灰を釉薬にしてできています。どこかに桜色が現れています。 |
||
 |
 |
| No.14 アカテガニを描いた壷をだいた一輪挿し いろいろな形にアカテガニのついた壷を抱かせました。中は空洞なので、水がたくさん、入ります。大きさは10cm程度、小さい空間を飾って下さい。 |
|
|
番外 |

|
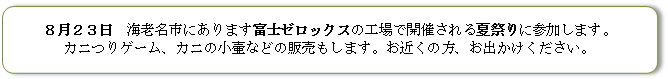
*1 現在「アカテガニ募金」はNPO法人小網代野外活動調整会議が預かり、トラスト財団に寄付をしています。
*2 現在カニパトロールはNPO法人小網代野外活動調整会議が実施しています。
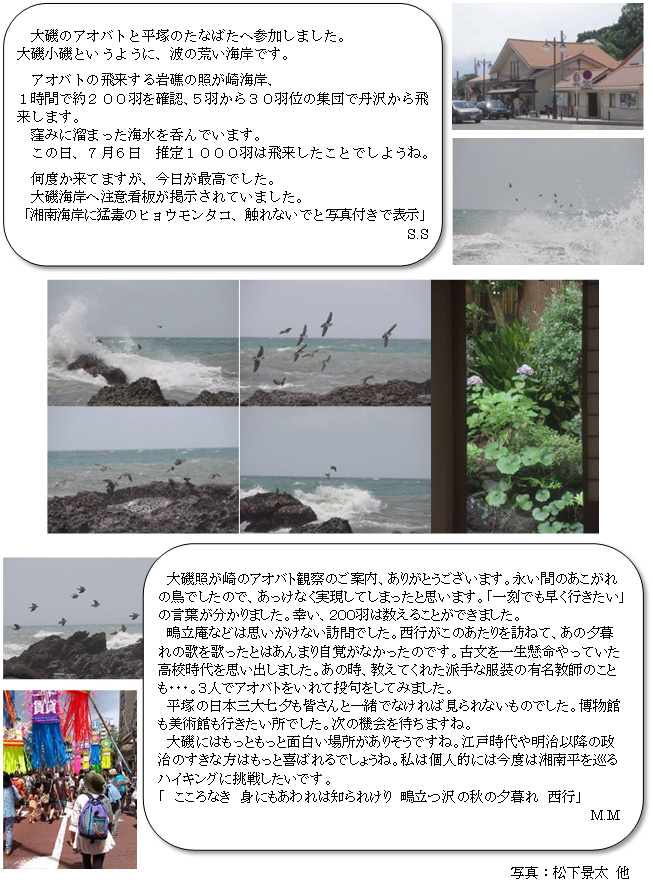
| 4/29 | スタッフ会議(引橋 総合福祉センター) |
| 5/12 | 鶴見川源流祭に出展 |
| 5/12 | 公益社団法人日本ナショナルトラスト協会全国大会参加 |
| 5/18 | 通信128号印刷(横須賀市市民活動サポートセンター) |
| 6/1 | 公益社団法人日本ナショナルトラスト協会総会に出席 |
| 6/15 | 第115回自然観察&クリーン「小網代干潟のカニと貝 ヤドカリもね!」 |
| 日 時 | 2013年8月25日(日)13時30分~15時30分 | |
| 場 所 | 三浦市初声市民センター講義室(京急・三崎口駅下車 徒歩15分・バス 下宮田下車1分> | |
| 第1部 | 総 会 | |
| 第2部 | 記念講演 「25年春 小網代一般開放にむけて」 岸 由二氏(NPO法人小網代野外活動調整会議代表理事 慶應義塾大学名誉教授) |
|
| 会員さまには是非、ご参加下さいますよう。なお、ご都合がつかない場合は、メールにてお知らせしました委任状の送付を24日までに お願いいたします。 | ||
| 会の活動費 | 杉崎泰章様 大高義彦様 須田漢一様 柿島京子様 安西章次様 野本哲夫様 鈴木カヲル様 須藤伸三様 盛野成信・雅子様 祖父川清治様 加藤利彦様 SHIO2様 宮本美織様 橋美千代様 鈴木清市様 |
| 森の応援金 | 杉崎泰章様 奥津信子様 田中幹人様 蓮尾もと子様 岸 修様 土屋圭子様 辻 晴一様 ジポーリン菜穂子様 ジポーリン周樞様 河内町子様 佐藤 高様 木内恭子様 山本勝久様 大泉繁子様 加藤紀子様 福田みどり様 藤崎英輔様 山本述子様 藤野秀代様 高橋宏之様 岡見義昭様 上田尚美様 坪田弥乃子様 北村和子様 三本保子・裕子様 金木公子様 大塚 敏様 須藤伸三様 倉内太輝様 盛野成信・雅子様 吉永浩三様 高間玖爾美・玲江様 大川須美様 小倉雅實様 柴田朱美様 SHIO2様 西川次代様 小田島一生様 飯田久仁子様 橋美千代様 橋ちひろ様 仲澤イネ子様 浪本晴美様 浪本梓様 |
| 以上の方からご寄付をいただきました、ありがとうございました | |

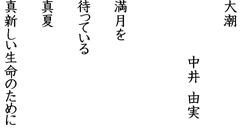
Ⅰ期: 7月27日(土)・28日(日)● カニパトに参加されるにあたって、ご注意いただきたいこと
Ⅱ期: 8月10日(土)・11日(日)
Ⅲ期: 8月24日(土)・25日(日)
17時~20時、小網代湾奥・アカテガニ広場で実施します。
実施要領、注意事項、装備については必ず事前にNPO法人小網代野外活動調整会議ホームページの情報をご確認ください。
当日荒天(雨・強風・波浪・雷等)により、観察中止になることがあります。
(中止決定次第、ホームページhttp://www.koajiro.org/に掲載されます。)
森の中にトイレはありませんので、事前に森の外でお済ませください。
(三崎口駅構内トイレ、シーボニア前公衆トイレが拝借できます。)
1時間ほど水の中に立って放仔観察をしますので、水に入れる装備(長靴が最適、 サンダル危険)、懐中電灯をご持参ください。
お問い合わせ
NPO小網代野外活動調整会議事務局
TEL: 045-540-8320
URL: http://www.koajiro.org/
 真夏の大潮の夜、アカテガニのかあさんたちが山をおりてきます。お腹いっぱいに抱えたあかちゃんが生きるためには海が必要だから、あかちゃんを海に放すには今夜がいちばんよい日だから、 かあさんガニはひたすら海を目指します。卵のように丸くなって母さんのお腹にいたあかちゃんは海に放たれるとすぐにゾエア幼生の姿で泳ぎだし、大潮の流れに乗って外海へと旅に出ます。人間の私たちは海の中から静かに アカテガニのお産を見守りましょう。そして旅立ち前のあかちゃん(ゾエア幼生)の姿や泳ぎも観察したいと思います。 真夏の大潮の夜、アカテガニのかあさんたちが山をおりてきます。お腹いっぱいに抱えたあかちゃんが生きるためには海が必要だから、あかちゃんを海に放すには今夜がいちばんよい日だから、 かあさんガニはひたすら海を目指します。卵のように丸くなって母さんのお腹にいたあかちゃんは海に放たれるとすぐにゾエア幼生の姿で泳ぎだし、大潮の流れに乗って外海へと旅に出ます。人間の私たちは海の中から静かに アカテガニのお産を見守りましょう。そして旅立ち前のあかちゃん(ゾエア幼生)の姿や泳ぎも観察したいと思います。 |
||
| 日 時 | : | 8月10日(土)(中止の場合は8/11順延) |
| 集 合 | : | 16時 三崎口駅前(トイレがありませんので必ず駅で済ませてください) |
| 解 散 | : | 21時 三崎口駅前解散 |
| 持ち物 | : | 長靴、お弁当、飲み物、雨具、虫よけスプレーなど防虫グッズ、懐中電灯 着替え |
| 参加費 | : | 無料 |
| 申し込み | : | 当日現地で受け付けします |
| ① 徒歩コース | : | 駅から干潟まで、スタッフの案内で三戸浜の眺望を楽しみながら、30分くらいの道のりを歩きます(熱中症対策を十分にお願いします)。 |
| ② バスコース | : | 駅からバスで12分、シーボニア入口から白髭神社を通って干潟に出ます。 (スタッフが同乗します) * バス料金は片道260円、ファミリー割引期間中なので、(現金・PASMO・Suica・回数券でお支払いの場合)大人1名につき小学生のお子さん1名が無料になります |
| ※ | ①、②どちらのコースも小網代の森と干潟を守る会のスタッフが往復のご案内をいたしますが、干潟ではNPO法人小網代野外活動調整会議のカニパトロールに参加していただきます。 |
| ※ | 雨にかかわらず、荒天(強風・波浪・雷等)の場合、観察中止になることがあります。 (カニパトを主催するNPO法人小網代野外活動調整会議の判断に従います。 中止決定次第、ホームページhttp://www.koajiro.org/に掲載されます。) |
| ※ | ご参加の際は、上記・NPO法人小網代野外活動調整会議のお知らせにある「●カニパトに参加されるにあたって、ご注意いただきたいこと」を必ずお読みくださいますよう、お願いいたします。 |
|
小網代 森と干潟つうしん NO.129 2013年7月20日発行 森も海も干潟も 奇跡の集水域生態系を未来の子どもたちへ |